二つの『ブレードランナー』の音楽
- Takeda Hirotsugu
- 2017年11月6日
- 読了時間: 5分
今回はちょっと趣向を変えて映画の話題です。
話題の『ブレードランナー2049』を見てきました。
これ、とにかく情報量が多い映画です。そのくせというかだからこそというか、余計な説明は一切ありません。説明的な台詞もほぼゼロです。
それでいて、上映時間が2時間40分以上もありますから、最後の方になると疲れちゃって結構注意散漫な状態で見ちゃうことになります。少なくとも僕はそういう状態になりました。
多分、見落としや勘違いが相当あるんじゃないかと思って翌日もう一度見に行ったんですが、予想通りいろいろ見落としてましたね。多分、よほど集中力がないと、途中でストーリーを見失っちゃう人もいるんじゃないでしょうか。
ところが、ネットの評判とか読むと、大体似通った感じの肯定的な意見が大多数を占めてる割に、そこそこ重要と思われるところを見落としてる人も少なくないようです。つまり、見落としたら見落としたままでも映画全体の印象はそんなに変わらないのかも知れないということなわけですね。
実際、僕も1回目と2回目でそんなに印象は変わらなかったんです。ラブとかジョイとか個々のキャラクターの印象はちょっと変わりましたけど。
僕は前作『ブレードランナー』が大好きで、映画館で10回以上、ビデオやDVDを含めれば50回近く見ています。
映画そのものの完成度というか仕上がりの良さは間違いなく今回の『ブレードランナー2049』の方が上だと思うんですが、だからといって『ブレードランナー2049』を10回も20回も見るかというと、多分見ないと思うんですね。
DVDが出たら間違いなく買うくらいには気に入ってますが、5回は見直さないだろうな、っていう感じです。
これはなぜだろう、と思って家でもう一度82年の『ブレードランナー』を観ていて気がつきました。
「音」の自己主張がすごく強烈なんです。
露店で流れているラジオの音楽、様々な言語が入り混じった街角のノイズ、機械類の動作音、一つ一つの台詞、映画の中に存在する全ての音が、ヴァンゲリスの音楽によって一つにまとめ上げられているような感じさえあります。DVDを持っている人は是非一度やってみて欲しいんですが、映像を見ないで『ブレードランナー』を流しっぱなしにすると、音楽と効果音のバランスや台詞と音楽が被さるタイミングが入念に設計され、音だけでも一つの大きな流れが作られていることがわかります。
その一方で、映像は薄暗かったり雨が降っていたりで、画面の隅から隅まではっきり見えるシーンがほとんどありません。凝りまくって細かいところまで作り込んだセットを敢えてぼんやりとしか見せない代わりに、あのロサンゼルスの街角で聞こえるであろう音を隙間なく配置してあるんです。この演出が没入感を生み出してるんですよね。
いわば、「視界が悪い分、環境音に対して敏感になっている状態」をスクリーンの中に再現しちゃってるわけです。その状態で、無機質さと叙情性の絶妙なバランスで成り立つヴァンゲリスの音楽が『ブレードランナー』の世界観を暗示するわけです。
これは絶対リドリー・スコットが意図的にやったことだと思います。
未来都市をこういう形で描いたSF映画は『ブレードランナー』が初めてでしたから、まず観客を「2019年の荒廃したロサンゼルス」という舞台に引き込んでしまわないことには、「人に作られた人のようなモノ」と「人らしさを失っている人」の対比というテーマが嘘くさい絵空事になると思うんですね。デッカードであれ、ロイであれ、あるいはJFセバスチャンであれ、『ブレードランナー』の登場人物だちは82年に生きている生身の人間にとってリアリティを持った存在にはなりにくいキャラクターでした。
「雨がずっと降っていて、薄暗くて薄汚くてジメジメした、不健全で不健康な未来のロサンゼルス。そこに人間そっくりの「人間もどき」を殺すことを仕事にしていた男がいた」なんて言われても「は?」って感じになっちゃうと思うんですよ、普通は。
映像と音が渾然一体となった世界を体感して、はじめてキャラクターたちの内面を意識できるようになるんですね。
で、『ブレードランナー2049』なわけですが。なんか音楽は影が薄いです。印象に残ったのは『ブレードランナー』の曲をアレンジした曲と、効果音的な「ブオーン」とか「ドゲゲン」とかいう音、そしてジョイが起動する時の「ピーターと狼」くらいですかね。
ハンス・ジマーとベンジャミン・ウォルフィッシュの音楽に個性がないわけじゃないんです。サントラで聞くと、むしろかなりいいです。つまり、映画の中で聞くと影が薄いっていうことなんですね。
なぜそうなるかといえば、結局のところ映像でいろいろ見せすぎちゃってるんですよ。僕が見終わった途端に「見落としがいっぱいあったかも」と思ったのもそれが原因です。目で見て脳で処理しないといけない視覚情報がとにかく多いので、音にまで気が回らないんじゃないかと思います。
『ブレードランナー』はビデオが売れて再注目されることになったというのは有名な話ですが、当時、日本でも輸入盤の字幕なしのビデオを買ってたファンが少なくなかったんですよ。
今はなき六本木のWAVEとか、新宿のすみやとかで扱ってたんですが、2万円を軽く超える値段がついてたにも関わらず、あっという間に売り切れちゃったんですよね。
僕の友達に2も人ほど輸入盤のビデオを買っちゃったマニアがいたんですが、彼らは別に英語が堪能だったわけじゃありません。「台詞はわからなくても(映画館で何度も見てストーリーは頭に入ってるわけですが)、音と映像を何度も自室で楽しむ」ために、学生アルバイトの時給が500円とか600円とかの時代に2万数千円のビデオソフトを買っちゃったわけです。
『ブレードランナー2049』は多分、そんな熱狂的なファンを生まないと思います。
完成度は高いですし、ユニークな作品であるのも間違いありません。
完成度やユニークさは、どれくらい愛されるかとはまた別の問題ということなんでしょうね。



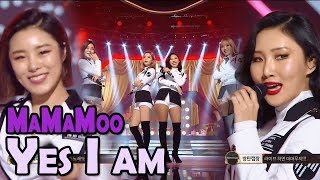









コメント