韓国の「シブヤケイ」の話 その6
- Takeda Hirotsugu
- 2017年10月12日
- 読了時間: 2分
話がだいぶ長くなってしまったので、ちょっとまとめます。
2000年代に入ってから、徐々に韓国のインディーズが注目されはじめ、2006年〜2007年頃にはそれらの総称として「シブヤケイ」という言葉が使われるようになりました。
韓国の「シブヤケイ」という言葉は、日本の「渋谷系」よりも更に定義が曖昧でなんだか良くわからないところもありましたが、概ね「歌を主役にしない音楽」あるいは「楽器音が声と同等以上に重要視されている音楽」のことを指していたと考えてもさほど間違ってはいないように思います。
この曲なんて歌よりバックの音の方が印象に残りますよね。
こういう音楽の作り方でアイドル歌謡を作ったらどうなるか、という見本がSUPER JUNIORの「Sorry Sorry」でした。
この曲のバックトラックは同じパターンを延々繰り返しているだけで、ドラムのパターンとボーカルのメロディで多少変化をつけている程度なんですが、それがかっこいいポイントになってるんですよね。 僕は男のグループにはほぼ興味ないんですが、この曲には結構びっくりしました。
これってアイドルハウス?みたいな印象でしたね。
ただし、こういう曲調はかっこいいダンスと、キーになるポイントでちゃんと歌えるメンバーがセットになっていないと、退屈なだけの曲になってしまうリスクもあります。
モロにそういう部分で大失敗こいちゃったのがこれですね。
一度解散したRooraが再結成して発表した曲なんですが、色々勘違いしちゃってる節が随所に見受けられます。
これは往年のRooraファンにとってもほぼ黒歴史に近い曲で、結局この曲が収録されたアルバムがRooraの最後のリリースになってしまいました。
いや、昔は本当にかっこいいグループだったんですよ。
「Sorry Sorry」の成功はその後SHINeeにも引き継がれ、ガールズグループでもf(x)のようなグループが登場します。
全部SMエンターテインメント所属のグループですが、これは偶然じゃないでしょう。
80年代後半〜90年代に成立したダンスミュージックの手法は、デジタル楽器が低価格化した時期と重なっていたこともあり、フォーマットがほぼ世界共通になっていましたから、海外市場を狙って行くには好都合だったんじゃないかと思います。
K-POPというとビジュアル面でばかり注目されがちですが、サウンドの方も長い年月をかけて売るための工夫を続けて来たわけです。その工夫が空回りしちゃってることも多々ありますが、そういう試行錯誤がK-POPの面白さを支えているんじゃないでしょうか。



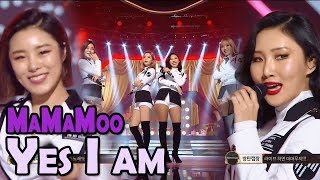









コメント